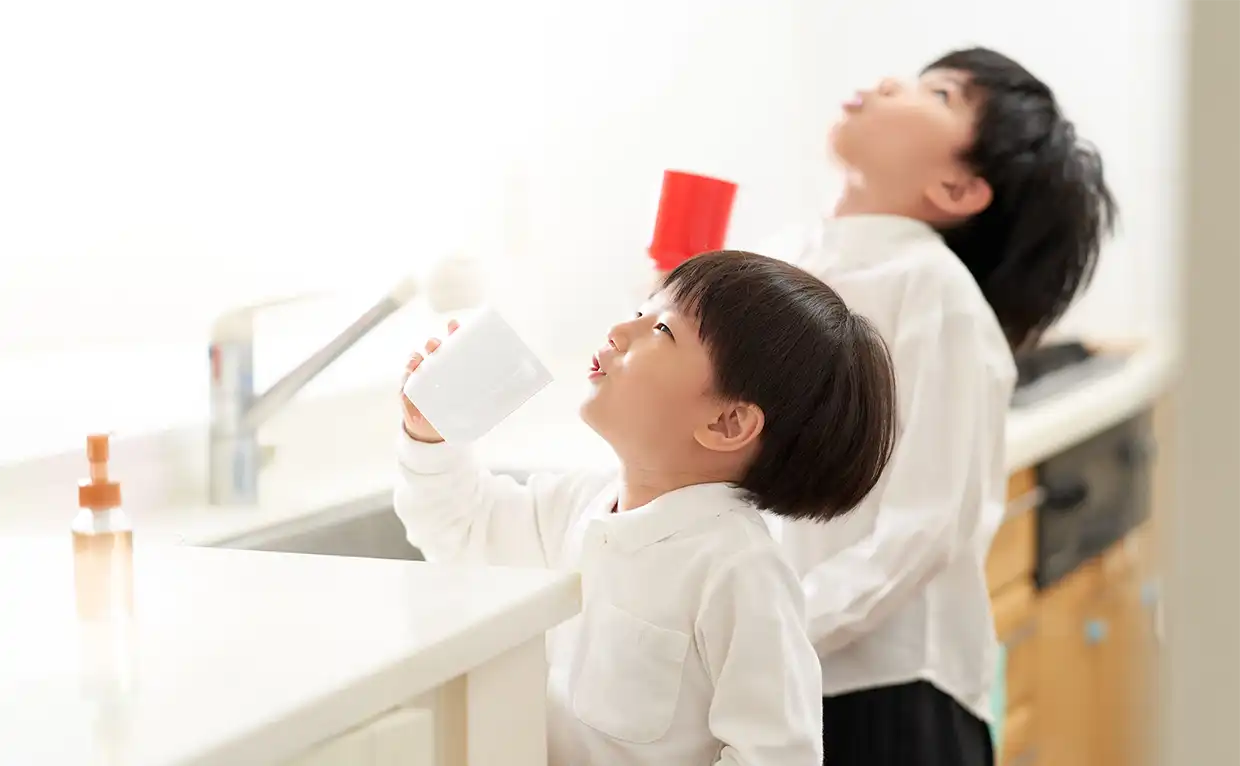すこやかな毎日へ。
まずは正しい知識から
「健康管理ラボ」はすこやかな毎日に役立つ情報を集めたサイト。健康にまつわる話題や、健康維持に役立つ乳酸菌や栄養素などの情報をわかりやすくご紹介します。

健康管理に役立つ
いろいろ
気になる『キホン』をまずはクリック!
-
乳酸菌の
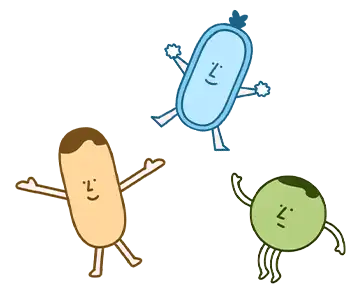
なぜ乳酸菌は体にいいの?知られざる乳酸菌のすごいパワーを解説します。
乳酸菌のキホンを読む -
免疫の

私たちのからだを守ってくれる免疫機能について理解を深め、さらに健やかな毎日を。
免疫のキホンを読む -
健康管理の

健康の知識や病気の話など、不安を解消するための情報を集めました。
健康管理のキホンを読む -
栄養の
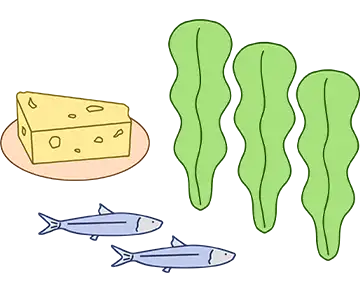
すこやかな毎日を支える栄養のキホンを知って、もっとおいしく楽しい日々を。
栄養のキホンを読む -
科学の

健康に関する科学のキホンを解説。気軽に生活に取り入れられる情報もお伝えします。
科学のキホンを読む -
からだの
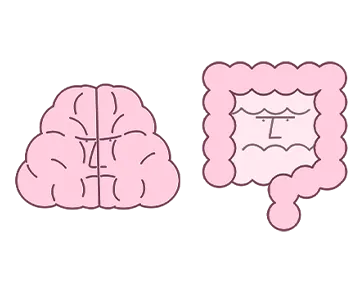
自分自身のからだのキホンをよく知って健康的な生活を送りましょう。
からだのキホンを読む